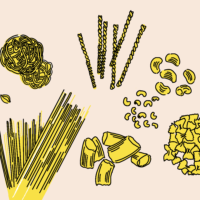なぜフレンチはバター、イタリアンはオリーブオイルなのか?歴史を彩る油をめぐる構図|食の起源
地中海式食事法がユネスコの無形文化財に指定されて以来、オリーブオイルの人気は地中海世界のみならず世界中でうなぎのぼりである。20年前には考えられなかったほど、日本の食卓にもオリーブオイルは浸透している。しかし、歴史をめくれば地中海世界といえどもオリーブオイルに固執した事象ばかりではないのである。

古代世界は3種の油の三つ巴
古代ローマの時代、オリーブオイルは農耕民族であったローマ人にとっては食卓に欠かせない油であった。
そのローマ人が、「蛮族の油」と呼んでいたのがバターとラードである。1世紀のローマ社会で博物学者として活躍したプリニウスは、バターについて「異民族が、われわれのオリーブオイルのように使用する油」と定義している。また、プリニウスは異民族がバターを食するだけはなく、肌に塗布する使用法を実践していることも記している。
バターを美容に使用する方法は、その後ローマの貴婦人たちのあいだでも流行したようである。さかのぼれば、古代ギリシア人たちもアジアから輸入したバターを肌に塗るものとして愛用していた歴史がある。
もうひとつ、蛮族の油として知られていたラードについては、記述を残しているのは共和政時代の農学者カトーただ一人である。ラードは、当時のローマ人には縁の薄い油であったのだろう。
そもそも、ローマ社会では豚を食べるという風習自体が存在しなかった。豚が食材として普及していたのは、当時はガリアと呼ばれていたフランスのあたりである。ユリウス・カエサルのガリア制服によって、彼らの風習も南下してローマ社会にもたらされる。
ローマの皇帝が豚を口にするようになるのは、3世紀に入ってからなのである。
ラードは滋養強壮に
ところが、ローマ帝国の崩壊とともに狩猟を生業としていたゲルマン民族が幅を利かせるようになる。かつてのローマ世界の耕地は彼らによって荒らされて、食生活にも影響を及ぼさないでは済まされなかった。
中世に入ると、王侯貴族たちの狩猟がさかんになり、肉食は富裕層のシンボルとなっていく。こうして、豚から作るラードも蛮族の証としてではなく権力者の特権となるのである。ちなみに、中世にはラードは料理や菓子に使われるだけではなく、火を通さずに口にして滋養強壮剤としても口にしていたという。
とはいえ、もともとローマ世界に属していたイタリア半島に住む人たちにとっては、最も馴染み深かったのはオリーブオイルであったことに変わりはなかったようだ。
日常的に摂取できていたオリーブオイルも、蛮族の侵入によってオリーブの木が荒らされてしまうと以前ほど身近な存在ではなくなっていく。
中世の時代、豚は森といい街中といいあちこちで飼われていた最も一般的な家畜であった。そのため、貧しい人たちは豚からとったラードを一般的に使うことが多くなったのである。
キリスト教会も、美味しい油には勝てない
ところで、この油の使用に関してはキリスト教会も介入しているのが面白い。
カトリック教会には、復活祭の前に食の節制を義務付けられる「四旬節」が存在する。この間、肉類などの贅沢品の摂取は節制すべしという慣習である。
というわけで、肉から作るラードの使用も禁止されていた時代があった。とはいえ、オリーブオイルはその生産が減っていた時代と重なり、庶民には手が届かない。そこで、当時の人々はクルミの実から作った油を使用していたという記録もある。
ただし、このクルミの油は風味がよくなかった。
816年のアーヘン公会議で、フランク王国にはオリーブの木が育たないことを理由に、四旬節中もラードの使用を許可することが認められる。節制期間といえどもまずい油は口にしたくないという人間の希求を、キリスト教会が認めてしまったのである。地中海世界らしい融通の利かせ方が愉快である。
バターの存在価値
公会議でラードの使用が許可されたとはいえ、その使用を躊躇する善良な聖職者や庶民も存在していた。
オリーブオイルは入手不可能、ラードは禁忌、クルミの油はまずいという状況に置かれた人々の救いとなったのが、バターの存在であった。8世紀のフランク王は、四旬節に食べてもよいものリストにしっかりとバターを加えている。
そして15世紀、なぜかイタリア半島でバターが大流行するのである。現代の栄養学者は、この現象を「2度目の蛮族の侵入」と呼んでいる。この現象の理由は明確ではない。
一説には、15世紀初めに法皇となったマルティヌス5世に仕えた料理人にあったといわれている。この料理人は、ヨハネス・ボッケンハイムというその名からもわかるドイツ人であった。
ローマでも有数の貴族であったコロンナ家出身のマルティヌス5世は、根っからのローマっ子であったはずである。その彼に、バターの美味を伝えたのがボッケンハイムであったのかもしれない。ボッケンハイムは、卵とバターの相性がよいことを世に知らしめたことでも有名である。
ラードの使用は、バターの流行に押されて減退した。しかし、まったくなくなったわけではない。
ミケランジェロが、大理石の生産地であったコロンナータのラードを愛したことでも知られるように、イタリア料理のなかでラードの存在はしっかりと残ったのである。ちなみに、大理石の箱の中で熟成するコロンナータのラードは、現在も高級品として健在である。
フランス王ルイ14世が流行させたバター
バターが大流行したとはいえ、地中海世界ではオリーブオイルが愛好され続けた事実は見逃せない。当時のイタリア人は、オリーブオイルとこれまた高価であった香辛料を組み合わせた料理が大好きであったのである。
ところが、フランスに太陽王と呼ばれるルイ14世が登場すると、オリーブオイルの形勢は悪化の一途をたどる。
ルイ14世は、スパイスを利かせた料理よりもバターを使った料理を好んだためだという。当時のルイ14世の影響は、宮殿の建築様式からファッションにいたるだけではなく、食卓にも及んだのだろう。
このように、ヨーロッパ世界の食の流行は、えてして権力者によって左右されてきたのである。油も、その一事を示す好例といえるだろう。
日本でも安土桃山時代には油が料理に使われ始める
和食と油という組み合わせはあまりイメージとして沸いてこない。しかし古くは、徳川家康が天ぷらの食べすぎで死亡したという言い伝えがあるぐらいで、まったくのゼロであったわけではないのである。
実際、日本に油を使った料理が普及し始めるのは安土桃山時代といわれている。江戸時代にも、天ぷらを中心とする油の使用はある程度認められるものの、本格的に日本人が油を調理に使用するようになるのは明治以降といわれている。
油は使い分けてこそ美味
現代のイタリアでは、「北はバター」「南はオリーブオイル」という版図がはっきりしているといわれている。とはいえ、イタリア中の子供たちは「パスタビアンカ」と呼ばれるバターとパルミジャーノチーズを絡めただけのパスタが大好物だし、質の良いラードはブルスケッタに乗せるなどして今も愛されている。
オリーブオイル礼賛は世界中の風潮であるが、それ以外の油の良さも適した調理法でぜひ堪能したい。
EAT UNIVERSITY編集部が1店1店試食しセレクトした、手づくりグルメのセレクトショップ「3rd Menu by EAT UNIVERSITY」がオープン
“食を楽しみ尽くすための学校”をコンセプトに、様々なテーマについて取材を行ってきたEAT UNIVERSITYでは、そのネットワークと取材力を活かし、自分たちでその味を確かめ、本当に美味しいと思うお店の手づくりお取り寄せグルメだけを取り扱うセレクトショップ「3rd Menu by EAT UNIVERSITY」をオープンしました。
詳細はこちらから。
現在、3rd Menuのメールマガジンにご登録いただいた方に、全商品に使える5%OFFクーポンをプレゼント中
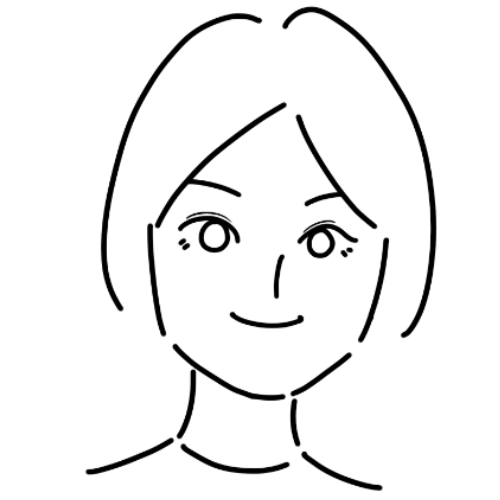
イタリアの片田舎で書籍に埋もれて過ごす主婦。イタリアに住むことすでに十数年、計画性なく思い立ったが吉日で風のように旅行をするのが趣味。美術と食文化がもっぱらの関心ごとで、これらの話題の書籍となると大散財する傾向にあり。食材はすべて青空市場で買い込むため、旬のものしか口にしない素朴な食生活を愛す。クーリエ・ジャポン、学研ゲットナビ、ディスカバリーチャンネルなど寄稿多数。