
世界の食文化から、アイデンティティーと食の未来を考える|食の上映室・番外編
食をテーマにしたTVプログラムが提供しているのは、世界の食文化や歴史を目で味わえる特別な体験である。スクリーンから登場するキッチンの心地よい音や彩り豊かな数々の料理に出会うと、食の奥深さに魅了されるはず。今回は「食べる」を軸にした作品のなかから「番外編」と題して、おすすめの書籍を紹介する。
KADOKAWA出版の『世界は食でつながっている You and I Eat the Same』は、デンマークのレストラン・ノーマ(noma)のシェフ、レネ・レゼピ氏などが綴る、食のエッセイ集である。

書籍には料理の香りや食卓の音が立ち上ってくるような写真が数多く掲載されており、目から楽しめる食の魅力をふんだんに伝えてくれる一冊だ。
変わりゆく食のアイデンティティ

知人の自宅でいただいた、バングラデシュの家庭料理(筆者撮影)
それぞれのエピソードでは、食をテーマにした19のストーリーが紹介されている。
パクチーやチーズ、コーヒーといった特定の食べ物をメインに語るストーリーもあれば、地域の食文化を丁寧に読み解くストーリーも満載だ。米国や欧州、そして日本など取り上げる地域は実に幅広い。しかしすべてのエピソードを読み終わると、家族や集団、そして社会のアイデンティティがいかに食によって形成されてきたのかという共通のテーマが浮かび上がってくる。
食には多彩で多様な魅力があることは、自明だろう。なかでも特に面白いのは、食にまつわるアイデンティティは、時代や地域によって変化しやすい「流動的な性質」をもつ点にあると感じる。十分な時間をかけると、かつてその土地に馴染みがなかった食べ物もやがては文化に深く根差し、新たな伝統を生み出してくれる。
「この土地に根を下ろしたものは、この土地のもの」と題したレネ・レゼピ氏のエピソードでは、約15年前のレストラン・ノーマのオープン時から大切にしている料理への想いや背景が綴られている。彼はユーゴスラビア紛争を経験しており、自身のアイデンティティに対して様々な葛藤を抱えている人物でもある。
そのなかで彼は「食も人もこの土地に育つものは、この土地のもの」という信念を掲げている。自分にとって馴染みの薄い食や文化、そして人々をどのように受け入れるのかは、人としてのあり方を問うテーマのようにも感じる。
ほかにも「行く先々でカレーは育つ」のエピソードを読むと、カレーライスがいかに文化的な寛容性を反映した食であるかが理解できる。インドやパキスタン、そしてバングラデシュには地域ごとに何百種類ものカレーが存在する。そのうえ、日本やタイ、アフリカの国々においても、その国独特のカレーやカレー文化が存在している。
世界では信じるものや政治的な立場、そして育ってきた環境が異なる人々が暮らしている。しかし食にはそれぞれの土地の物語や時代の背景を柔らかく伝えながら、必要に応じて形や味を変化させ、異なる人々を結びつける力をもっている。こうした力こそ、食のもつ最大の魅力なのかもしれない。
私たちは何を考えて、この先何を食べていくのか

ミャンマーの屋台で食した、お気に入りのデザート。 餅米とココナッツの相性がぴったり(筆者撮影)
『世界は食でつながっている You and I Eat the Same』を読むと、人間は食に対して「何をどのように食べるのか」「どのように味わうのか」という点に重きを置いていることも再認識できる。
何かを食べたり飲んだりするのは、単に生命を維持するだけでないことは多くの方も実感できるだろう。書籍のなかでは、身近にある穀物から試行錯誤して様々なパンを生み出す地域の住民や、北欧料理に合う醤油作りに励むシェフたちも登場する。
しかし現在は昆虫食や人工肉、そして3Dのフードプリンターなどが登場し、これまでの「食のあり方」が大きく変わろうとしている。私たちはこの先どのように食べて、どのように生きていきたいのだろうか。
これからの食生活、ひいては食文化を考える際には、筆者はそれぞれが自分なりの「食のものさし」をもつことがまずは最も大切だと感じている。
目の前の食事や料理を楽しみながら、自分が心地よいと思える食を求める。こうした所作は一見すると極めてシンプルだ。しかしインターネットで様々な情報を得られる現在では、「インフルエンサーや芸能人が紹介しているもの」「レストランやシェフの名が有名であるもの」が美味しいという考え方や意見が、多少なりとも浸透しているように感じるのだ。
私は海外旅行に行く際、ローカルな食堂やレストランでの食事を一番の楽しみにしている。地元の人々が毎日食べても美味しいと思えるメニューを、お腹いっぱいに頬張る。なかにはあまり口に合わない料理もあるし、高級レストランでしか味わえない料理もあるだろう。しかし何気ない日常の風景にこそ地域の食の魅力を知るヒントがあるのではないかという、私なりの「ものさし」がある。
現在国際的にも注目を集めているミャンマーに旅行した約5年前、私は機内で隣り合わせになったミャンマー人のおばあさんと意気投合し、現地の食堂や観光地を案内してもらった。ローカルな麺料理や餅米とココナッツのデザートなど、どれも心に染みる優しい味が本当に本当に美味しかった。
普段海外を旅行する際は身を守るうえでも警戒心を強くもっているのだが、彼女に対しては信頼できそうな「何か」を感じた。機内で共に過ごしたのはわずか数時間。限られた時間でこの「何か」を見極める判断軸や直感というのは、自分にしかわからない、そして自分にしか磨けない代物である。こうした「ものさし」は普段から様々な人に出会い、新たなものに触れる経験を積んでおかなければ得ることは難しい。
話を食に戻そう。世の中にはレストランや料理、そして食に関する情報があふれている。そして食べ物の味の良し悪しが存在することもほぼ間違いない事実だ。
しかし味覚というものは本来、育ってきた環境や地域によって個々人で差がある。自分の味覚によりシンプルに、自分の気持ちにより素直になって、自分なりの「ものさし」を通じて心地よい食事や料理を選び取る。こうした食の営みこそが、巡り巡って豊かな食文化を形成するのかもしれない。これからの食のあり方や未来を考えるうえでも、本書籍は様々な示唆を与えてくれた。
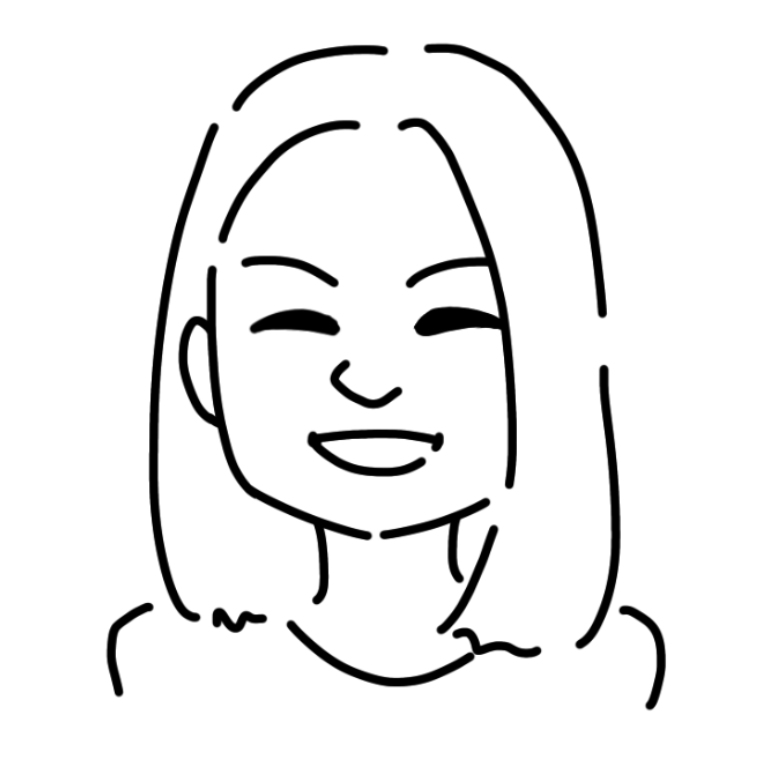
ライター、編集者。バングラデシュ、東京、宮城など複数の拠点で生活を送る。海外旅行に行く際はローカルマーケットと地元の食堂散策が欠かせない。トマトとナスとチーズが大好物。











