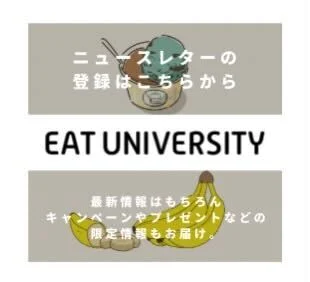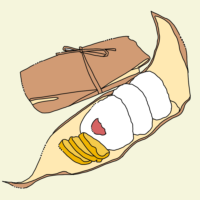古代ローマ軍の兵糧は生のレタス?ローマからはじまるサラダの物語|食の起源
世界中で誰でも食しているサラダ、そのサラダの発祥がイタリアにあることをご存知であろうか。
生の野菜を食べる「サラダ」という料理は、実は古代にまでさかのぼる歴史がある。こんな簡単な料理に歴史などあるのかと思われるかもしれないが、中世のイタリア人たちにとってはサラダこそが故郷の味であったことがさまざまな文献から判明している。
それはなぜだろうか?

レタスを植えるローマ軍
食の専門家によると、古代ローマの兵站学おいて欠かせなかったもののひとつにレタスがあるのだそうだ。ローマ軍は、兵の口を養うための兵糧を略奪に頼らず、陣営の周りに野菜や果物を植えて補ったことでも知られている。
ローマ軍が好んで陣営地の周りに植えた植物には、ぶどう、カルドン、レタスなどがある。ローマ人たちは、レタスを生で食べるサラダをことのほか好んだ。1世紀の詩人マルティアリスも、レタスについて触れた文章を残している。
当時、この生のレタスを食前に食べるか食後に食べるか、知識人たちは頭を悩ませたらしい。
当時食されていた野菜は、長い歴史の中で消えてしまったり品種改良されてオリジナルとは異なるものも多いといわれている。だから、ローマの人々が好んだ野菜サラダの実態については、実はすべてが明らかになっているわけではない。
故郷の味を恋しがる民族、それがイタリア人!
イタリア人というのは、食に関しては非常に保守的な民族である。
海外にバカンスに行くともなれば、マンマのお手製のトマトソース、エスプレッソコーヒー用のマキネッタと粉、ヌテッラ、パスタなどを大量にスーツケースに詰め込んだりする。
面白いことに、中世のイタリア人たちが外国に行って「ああ、お国のあれが恋しい」と思ったもののひとつが、「サラダ」なのである。
サラダなんて、ただ生の野菜を切って食べるだけではないかと思うだろう。
しかし、冷蔵や保存の技術がなかった中世、これができるのは大変なぜいたくであった。地中海式気候に恵まれたイタリア半島では、新鮮な野菜を食べる機会に恵まれていたために、ドイツやイギリスに赴いたイタリア人たちはサラダを恋しく思ったのである。
ちなみに、古代のギリシアでもローマでも、生野菜はオリーブオイルと酢と塩の味つけで食べていたことがわかっている。つまりサラダは、2000年このかた味付けが変わらない稀有なる料理でもあるのである。
1402年に登場する「サラダ」
ちなみに、イタリアではサラダのことを「インサラータ(Insalata)」と呼ぶ。
それと同義語と思われる「Salegiata」という言葉が登場するのは、なんと1402年のことである。ルッカ生まれの作家が記した小説に、お坊さんが野菜を摘んで生で食べるというシーンが登場する。これが、文献に登場するサラダの最初といわれている。
当時、イタリアから外国に赴いたインテリたちはこぞって「生野菜や果物が恋しい」と嘆いている。また、「サラダ」を意味する言葉さえ、イタリアの外には存在しないと書き残した医学者もいる。そして、この傾向はなにも中世からルネサンス時代だけに限らなかった。
近代の社会人類学者クロード・レヴィ=ストロースは、1968年に発表した『食卓作法の起源( L’origine des manieres de table )』の中で、「イタリアンレストランが世界中に広がったことによって、われわれは野菜を『生』で食べることを学んだ」と書いている。
つまり、生野菜をたべることは「実にイタリア的」であると、フランス人の学者が認めているわけである。
生で食べるイタリアの野菜とは?
フランス人のクロード・レヴィ=ストロースは、「元来フランスで生野菜といえばラディッシュくらいしかなく、それも大量のバターと塩で味つけされている。さまざまな種類の野菜を切って混ぜ、オリーブオイルを酢で味つけするイタリア風のサラダによって、われわれも生野菜に慣れつつあるのだ」とも書いている。
実際、イタリアのサラダは、地中海式食餌法がいかに健康かを実証するかのように大量に食べるのが特徴である。
中世からルネサンス時代のレシピを鑑みるに、当時の人がサラダとして食べていたのはルッコラ、レタス、アーティチョーク、ルリシチャ、ソラマメ、フェンネルなど多岐にわたる。
ちなみに、現在もオリーブオイルと塩コショウのシンプルな味付けで食べるフェンネルはその香りの強さから、ルネサンス時代には「ワインと相性が悪い」野菜としても名を残している。
たかがサラダ、されどサラダ
アメリカの作家マーク・トゥエインには、「無能な女にもできるもの、けんかとサラダ」といわれるほど軽く見られてしまったサラダであるが、イタリアの食通たちはされどサラダとばかりに、サラダへのこだわりを恥ずかしげもなく披露している。
バルトロメオ・スカッキやメッシブーコといったルネサンスのカリスマシェフたちがこぞってサラダのメニューを書き残しているほか、サラダを愛したインテリたちも「塩多め、酢少なめ、オリーブオイルたっぷり」の味つけが美味しいと語ったり、1627年にはアブルッツォ出身の医師が1冊まるまるサラダに捧げた著作『Archidipno, overo dell’ insalata e dell’ uso di essa』を残している。
味つけや野菜の組み合わせについても、よい年のインテリのおじ様たちがさまざまな意見を残しているのが楽しい。ちなみに、かのレオナルド・ダ・ヴィンチも、ルッコラについての草稿を残す。
マニエリズムの画家ポントルモの食日記にも、レタスのサラダは頻々と登場しているのである。
イタリア以外のサラダ
野菜をオリーブオイルや塩などのシンプルな味つけで食べるという風習は、研究によればギリシア人やローマ人だけではなく、ペルシア人やトルコ人、アラブ人も実践していたという。
しかし、彼らは生野菜だけではなく、ナスやホウレン草など火を通して食べる野菜もオリーブオイルやお酢で味つけをし、サラダ感覚で食べていたようだ。実際、ナスやホウレン草はペルシアやアラブからヨーロッパに持ち込まれ、ヨーロッパに普及した。
日本のサラダはどうであろうか。
日本にサラダが到来するのは、明治時代以降といわれている。日本では元来、野菜を生食するという慣習がなかったのだが、ある説によればとんかつに添えるせん切りキャベツがそのハシリなのだそうだ。
江戸時代後期、西洋からトマトをはじめとするさまざまな野菜が日本にやって来たが、レタスとキャベツの存在は日本のサラダにおける鉄板といえるだろう。また、大正時代後期にマヨネーズが日本に紹介されて、サラダはますます庶民にも身近な存在になったといえる。
ちなみに、日本でサラダに登場するキャベツやキュウリはヨーロッパではめったにお目にかからない。サラダ一皿にも各国の食糧事情が映されているのが面白いところである。
イラスト:おにぎりまん
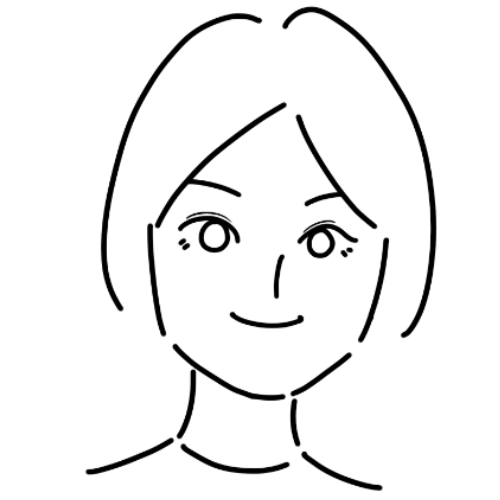
イタリアの片田舎で書籍に埋もれて過ごす主婦。イタリアに住むことすでに十数年、計画性なく思い立ったが吉日で風のように旅行をするのが趣味。美術と食文化がもっぱらの関心ごとで、これらの話題の書籍となると大散財する傾向にあり。食材はすべて青空市場で買い込むため、旬のものしか口にしない素朴な食生活を愛す。クーリエ・ジャポン、学研ゲットナビ、ディスカバリーチャンネルなど寄稿多数。